| ・kkomeさん発案の回路の例。 ・これ以上の「シンプル化はもう無理」などと言ってしまった不明に恥じ入るばかり。 ・究極のシンプル化ではないでしょうか。 ・その電圧ゲインの周波数特性を見ます。 |
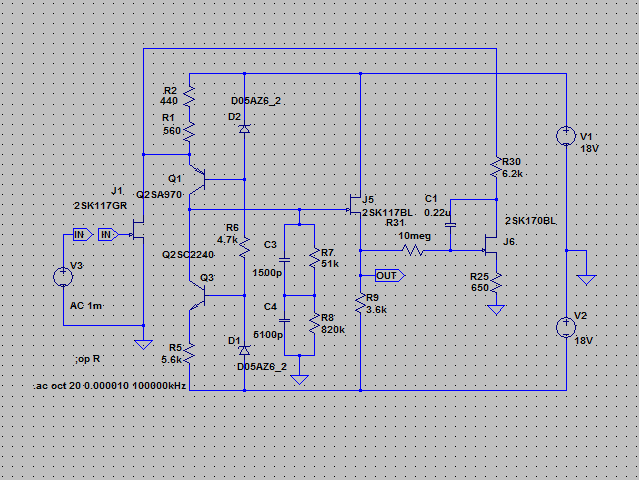 |
| ・そのゲインは、カートリッジVICである2SK117GR(実機では2SK97)のgm×EQ素子のインピーダンスで、他に関与しているものはありません。 ・本当に究極の無帰還IVC型イコライザーですね。 |
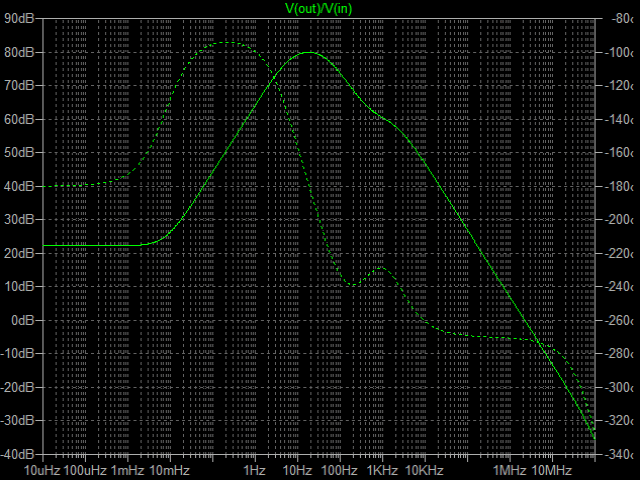 |
| ・1kHzのサイン波をカートリッジVICの入力に加えて、出力の応答特性を観ます。 ・入力レベルは、DL−103の1kHzの基準出力の0.3mVと3mV、4mV、5mV、6mV、7mV、8mV、9mV、10mV。 |
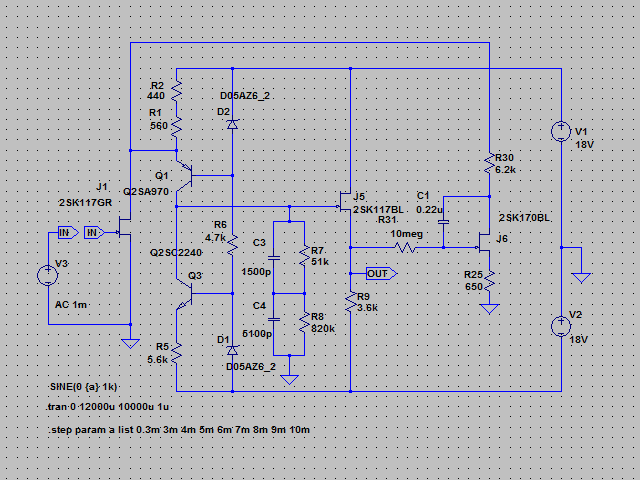 |
| ・素晴らしい。 |
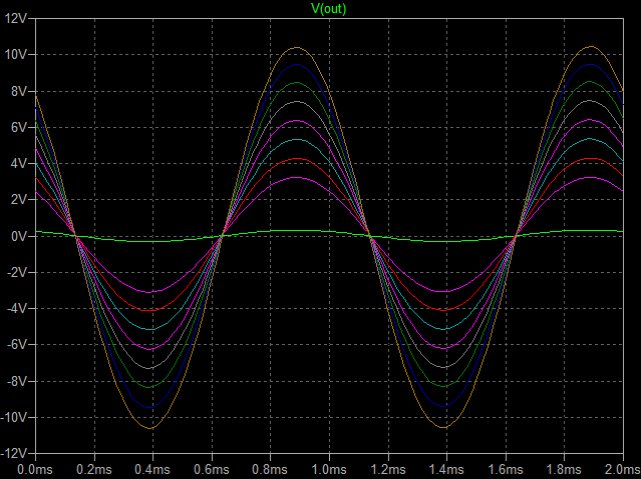 |
| ・マイナス電源に2kHz、1Vのサイン波を重複させて、マイナス電源をー18V±1V2kHzで変動する電源にします。 ・初段のツェナーダイオードに流す電流は定電流源で固定します。そうしないとツェナーダイオードの電圧が変動→初段動作点が変動→初段で波形が変動して話にならない状態となるので、そうならないようにしたものです。 ・その上で、2SK117も対アース動作にします。 ・I1は実際は定電流回路を組むわけですが、ここでは理想的定電流源にします。まぁ、理念形なので。 |
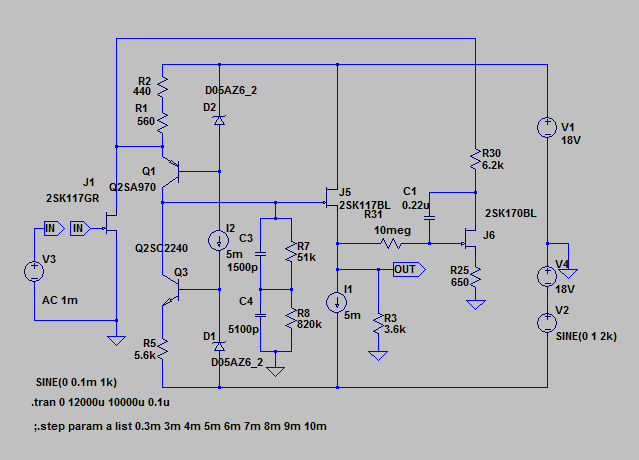 |
| ・これでも定電流回路Q3の電流値が変動しますね。 ・ですが、Q1の電流も、出力電圧も良好です。 |
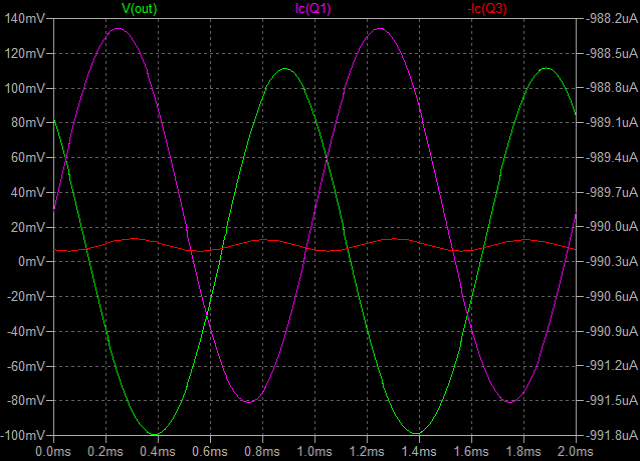 |
| ・問題のJ5の電流もOKです。 |  |
| ・kkomeさんご教示の通り、J5を対マイナス電源で動作させて、J5のドレイン電流でカレントラインアンプに信号伝達する場合は、EQ素子もマイナス電源につないで、基準点を同じにしないといけないんですね。 | 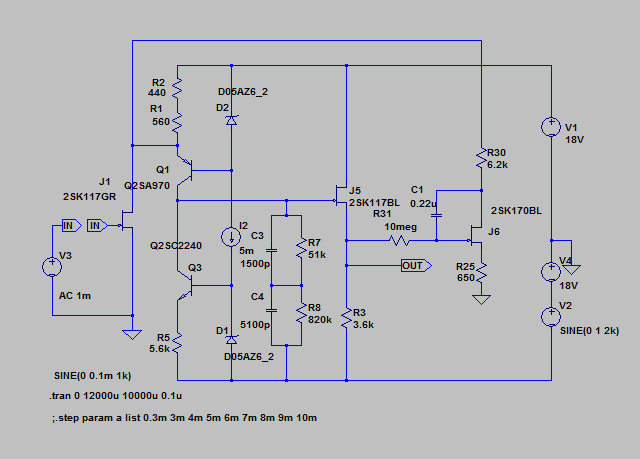 |
| ・J5ソースの出力電圧は完全にマイナス電源の変動に振られて、もう入力信号電圧伝達の体をなしていません。 ・が、赤のドレイン電流の方は、歪んではいるものの、信号の周波数と増幅レベルは正しいですね。 |
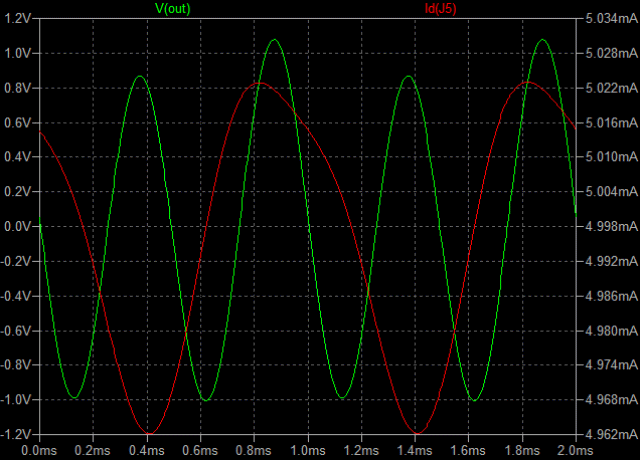 |
| ・これが、EQ素子をアースにつないだままであると、 | 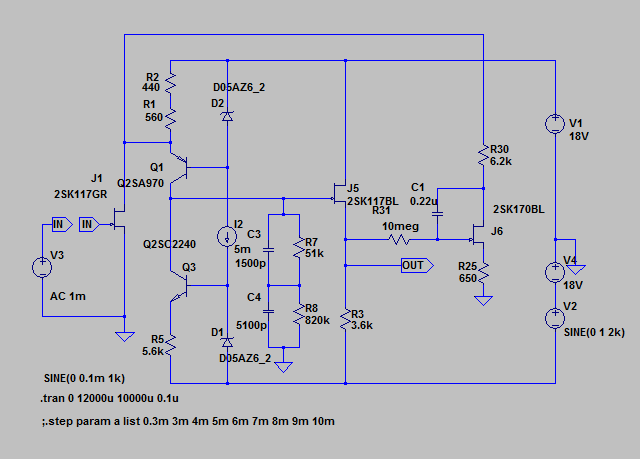 |
| ・J5ソースの電圧の方はマイナス側が膨らんだ歪んだ波形ではあるものの信号の周波数とその増幅レベルは正しくなりますが、 ・肝心のJ5のドレイン電流は、マイナス電源の±1V2kHzの変動/3.6kΩ=±0.27mV2kHzの変動となって、そのままJ5の出力電流に現れてしまっています。 ・これがkkomeさんご教示の内容(問題点)ですね。 |
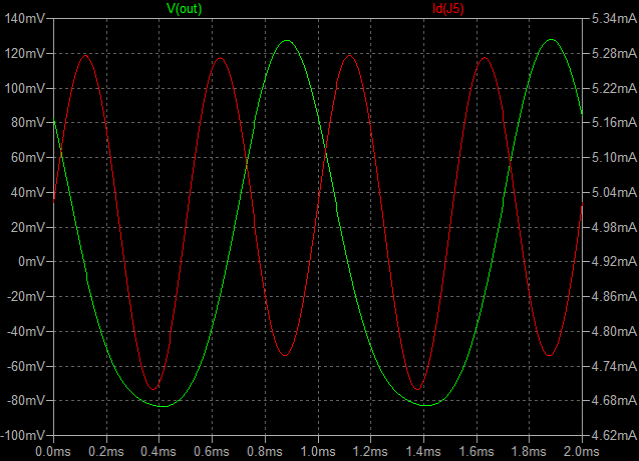 |
| ・ですが、レギュレータを使っているので、マイナス電源が±1Vも変動することは想定外です。 ・電源変動を1/10の±100mVにしてみます。 ・先ずはJ5も対アース動作とした、最良と思われる手法。 |
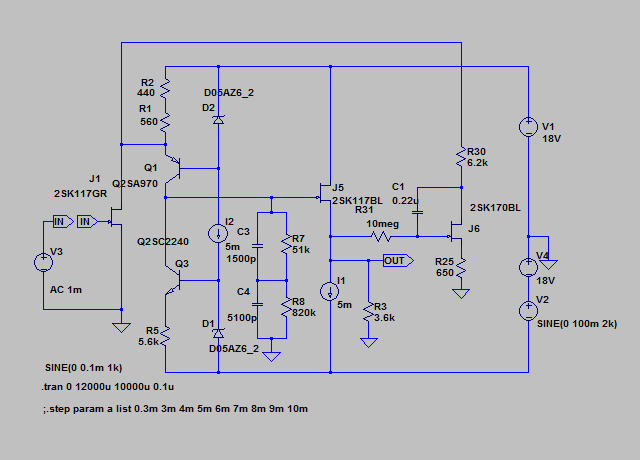 |
| ・良いですね。 |
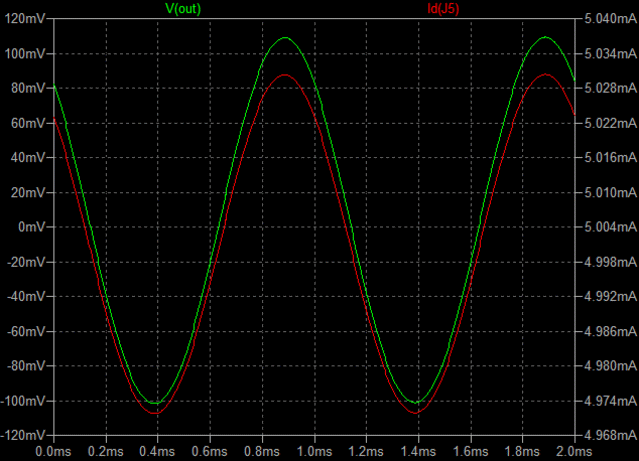 |
| ・次にEQ素子をマイナス電源に接続する手法。 |
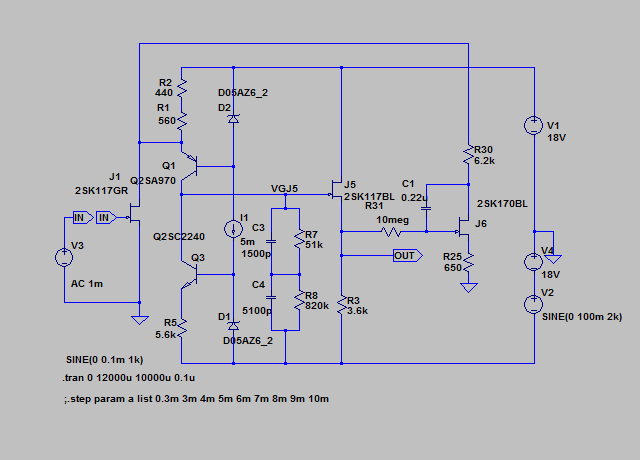 |
| ・J5のドレイン電流の方は全く問題ないですね。 ・J5を対アース動作にしないまま、信号をJ5のドレイン電流で伝達する場合は、これが正しい手法ですね。 |
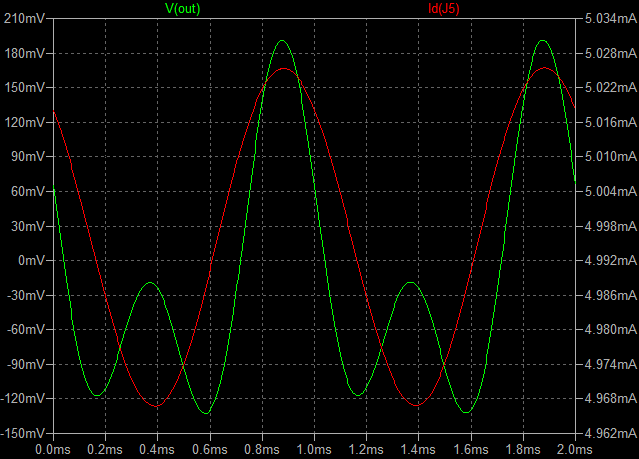 |
| ・EQ素子をアースに接続する手法のままだと、 | 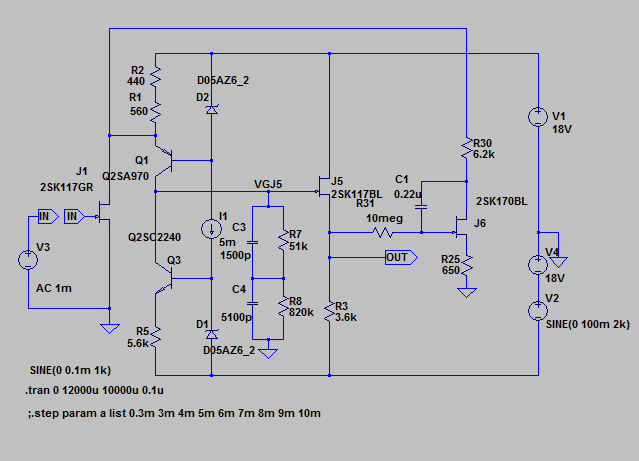 |
| ・J5ドレイン電流の1kHzの信号に2kHzのマイナス電源変動が乗ってしまいます。 |
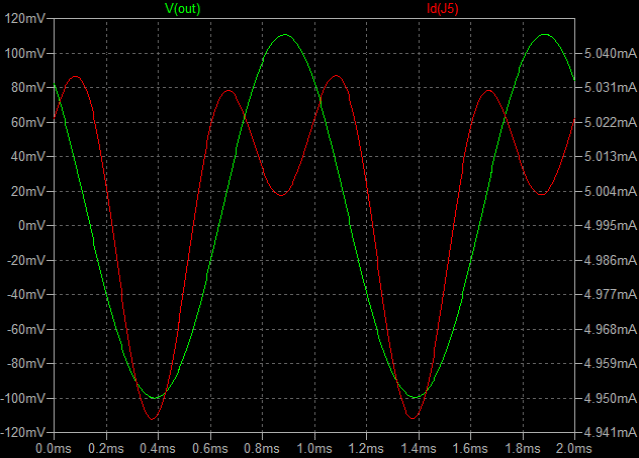 |
| ・電源変動を1/100の±10mVにしてみます。 ・先ずはJ5も対アース動作とする手法。 |
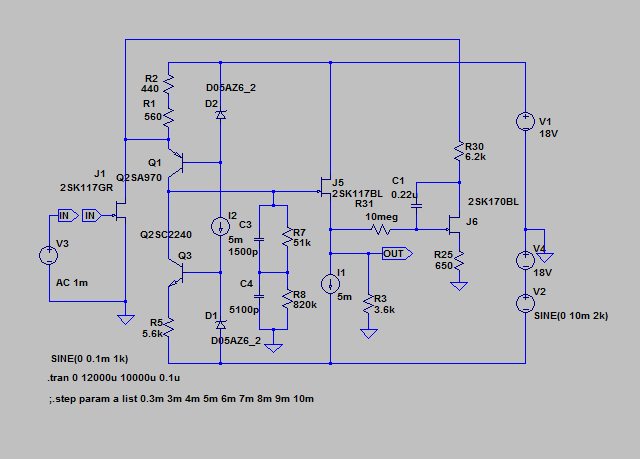 |
| ・当然問題なし。 | 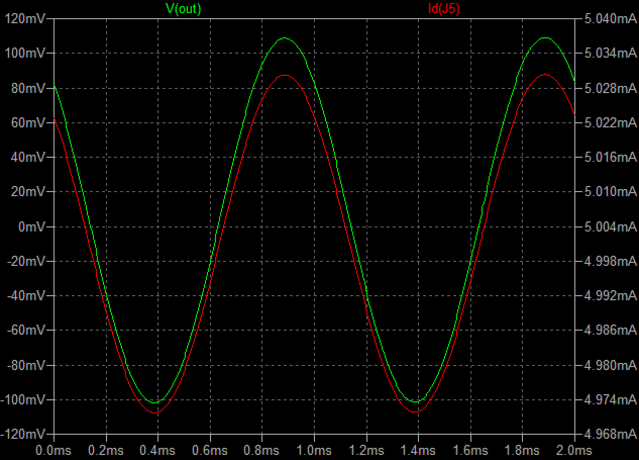 |
| ・EQ素子をマイナス電源に接続する手法。 | 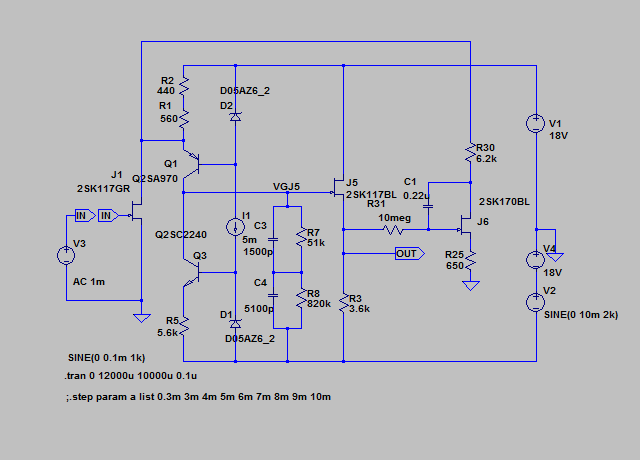 |
| ・電源変動が±10mVであれば、DL−103の入力レベルが0.1mVの信号レベルであると影響は小さくなって、出力電圧の方も視覚レベルで影響を確認できませんね。 | 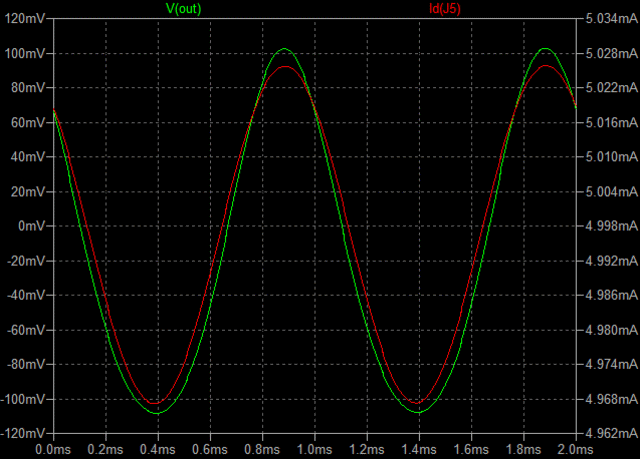 |
| ・EQ素子をアースに接続する手法のままでも、 |  |
| ・この場合も、DL−103の入力レベルが0.1mVの信号レベルであると影響は小さくなって、視覚レベルで確認できません。 |
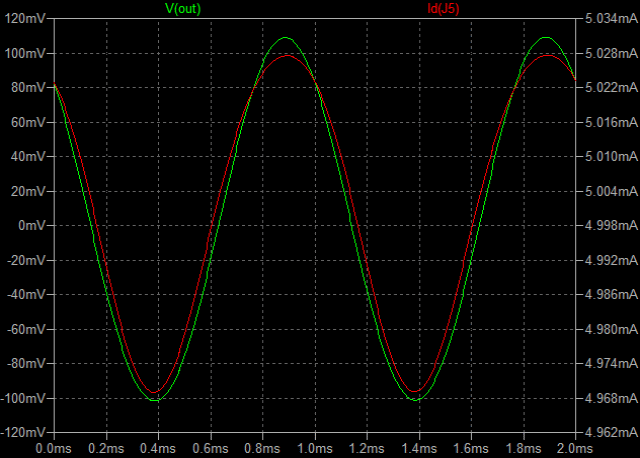 |
| ・ならば、これでもいいかな。 ・と、単純ではなく、入力レベルを1/10の0.01mVにすると、 |
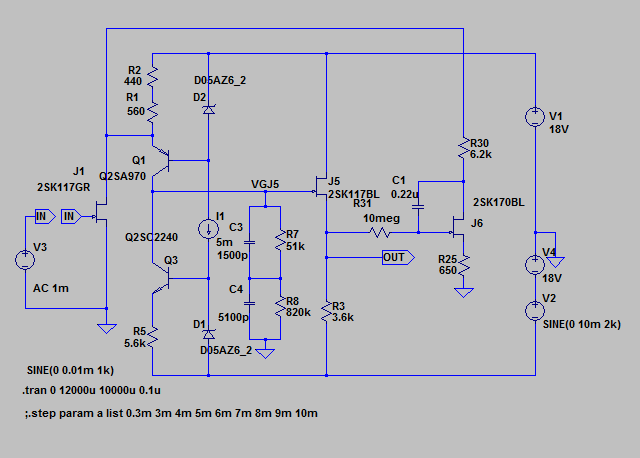 |
| ・しっかりJ5のドレイン電流にマイナス電源変動の影響が現れます。 |
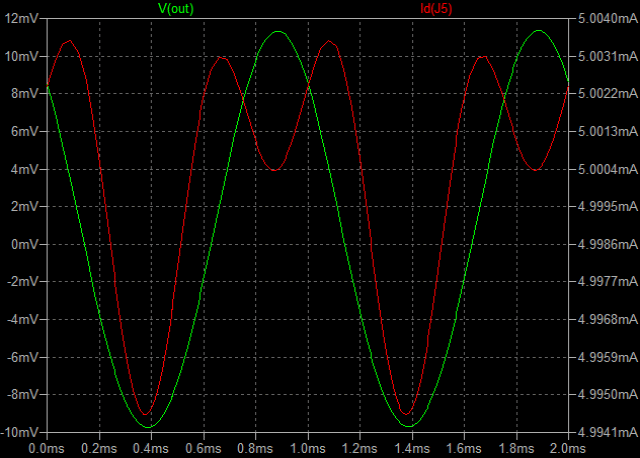 |
| ・レギュレーターは優柔だから±1mV程度の変動しかないのでは。 | 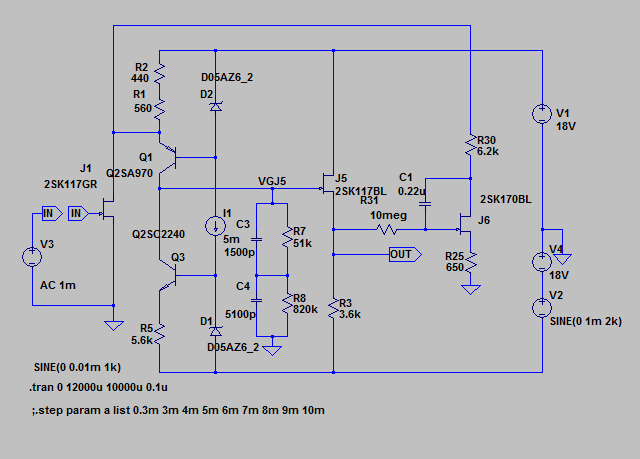 |
| ・そうであれば、0.01mVの入力であっても、影響は視覚的に確認できなくなります。 ・が、入力がさらに1/10の0.001mVになれば、同じように影響が現れ、その場合は電源変動がさらに1/10の±0.1mVになれば影響が確認できなくなるというように、この関係はずっと続きます。ので、問題が本質的に解消するものではありませんね。 |
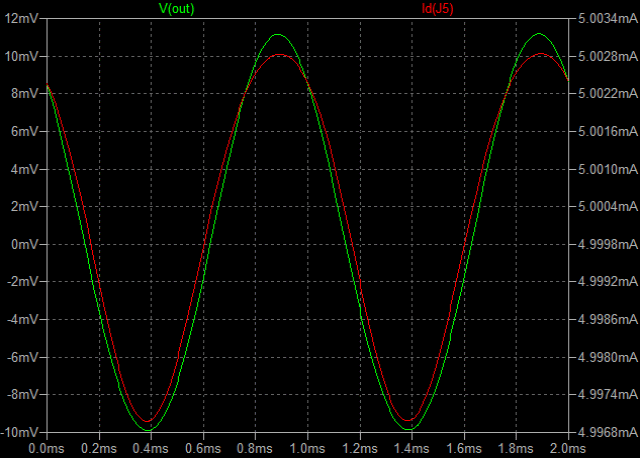 |
| ・初段からの影響がないように、電源変動の影響がJ5だけに及ぶようにして、J5のソース―ドレイン間電圧が一定になるようにしてプラスマイナスとも変動させます。 |
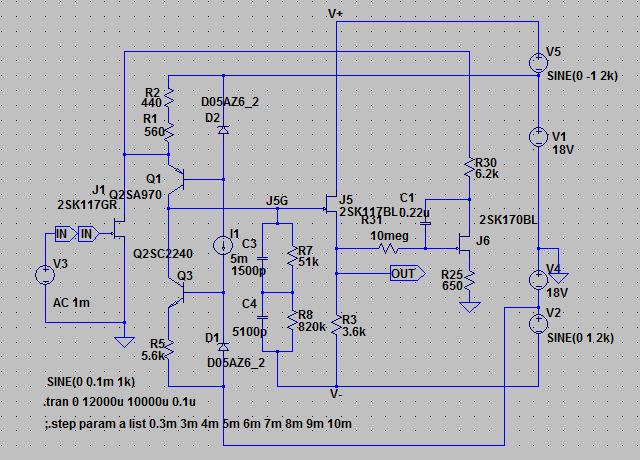 |
| ・J5の出力電流に生じる歪は同じようです。 ・J5のゲート−ソース間電圧が緑です。入力電圧そのものが歪んでいます。そして、これに基づいたJ5の出力電流のように見えます。 |
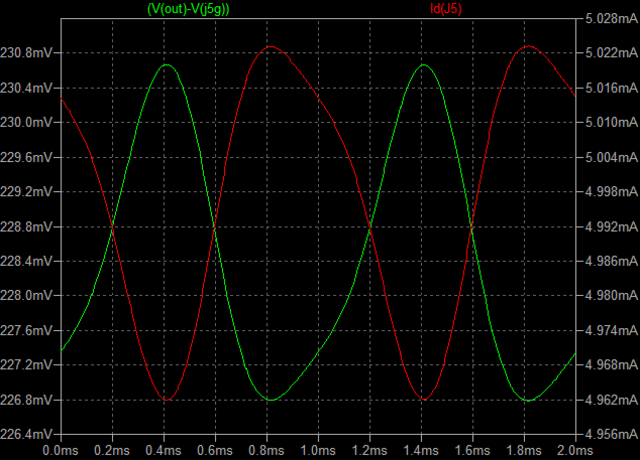 |
| ・EQ素子をオリジナル248の定数に変更します。 | 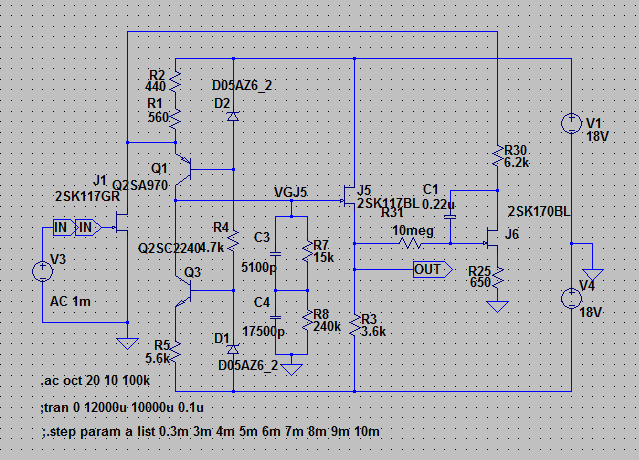 |
| ・EQ素子のインピーダンスが低くなるので、当然ゲインも小さくなって、1kHzで49.9dBです。 |
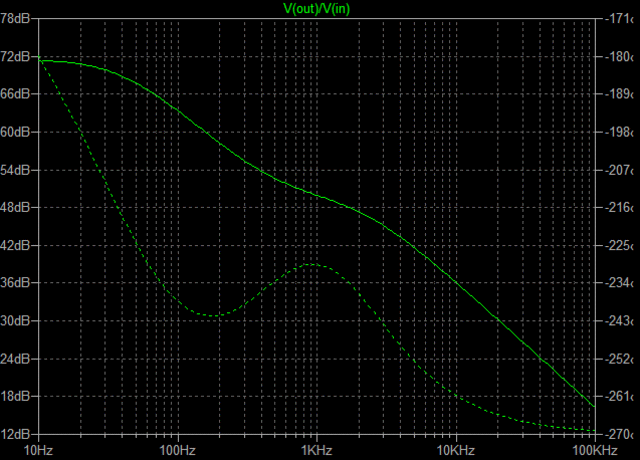 |
| ・ちなみに、オリジナルに忠実にR8を560kΩにすると、 |  |
| ・低域が過剰に上昇。 | 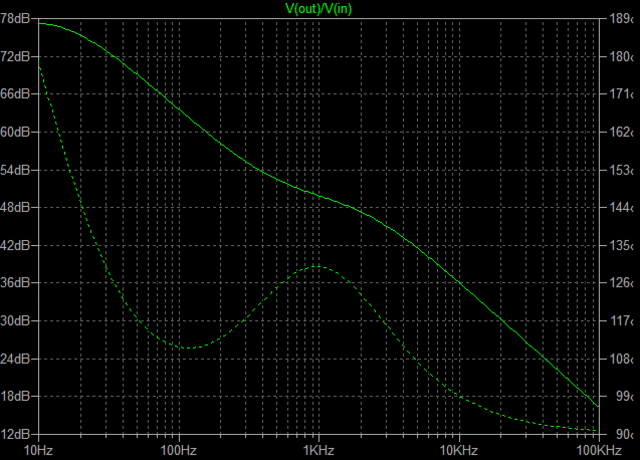 |
| ・他の影響を極力排除。 |
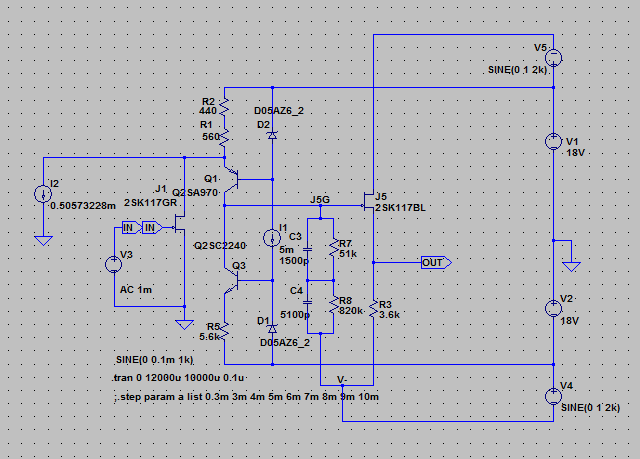 |
| ・上が、J5ゲートと負電源間、J5ソースと負電源間の電圧推移。 ・中がJ5ゲート−ソース間電圧推移。 ・下が、対アースのJ5ゲート電圧、J5ソース電圧の推移とJ5のドレイン電流の推移。 ・V(out)は2kHzの負電源変動で完全に振られていますが、J5のドレイン電流はかろうじて1kHzを保っています。歪んでいますが。 ・その歪はEQ素子の両端電圧から生じています。 |
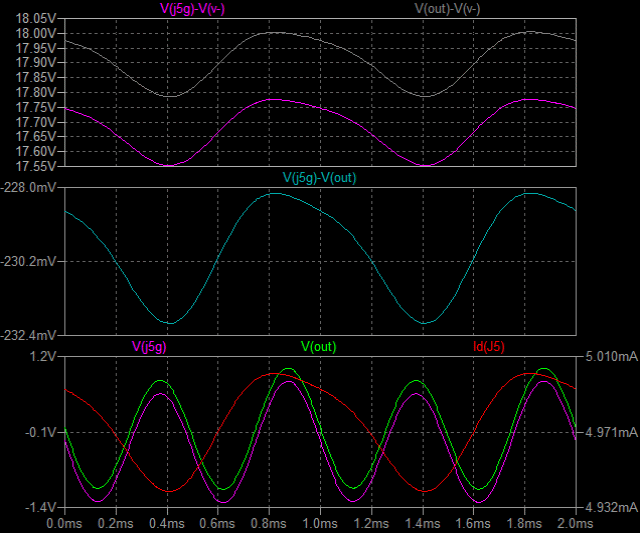 |
| ・もっと要因を探ります。 ・EQ素子の下にR4を加えました。EQ素子に流れる電流を観るためです。 ・最初にJ5のドレイン電圧変動の影響を観ます。 |
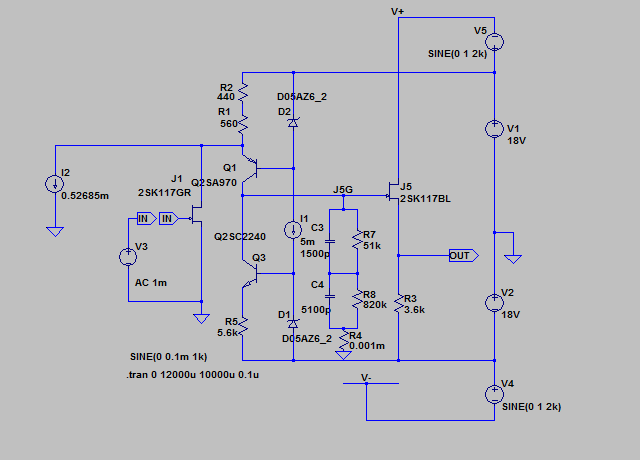 |
| ・上がQ1のコレクタ電流。 ・中がJ5のドレイン電流。 ・下がV(out)=出力電圧とEQ素子に流れる電流(I(R4))。 ・J5のドレイン電圧の変動は目視では確認できません。 |
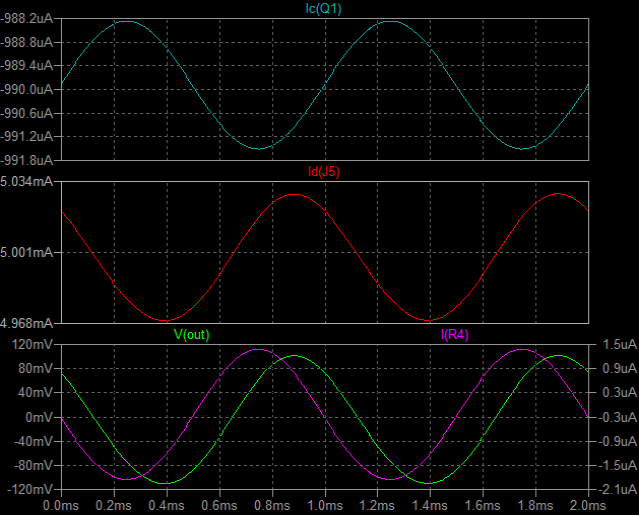 |
| ・入力信号を10kHzにしてみます。 ・入力側のQ1のコレクタ電流とEQ素子を流れる電流(I(R4)には影響が感じられませんが、出力電圧とJ5のコレクタ電流には正電圧変動の影響が表れています。J5のコレクタ出力抵抗が無限大ではないのでやはり影響はありますね。 ・が、その影響の程度は軽微そうです。 |
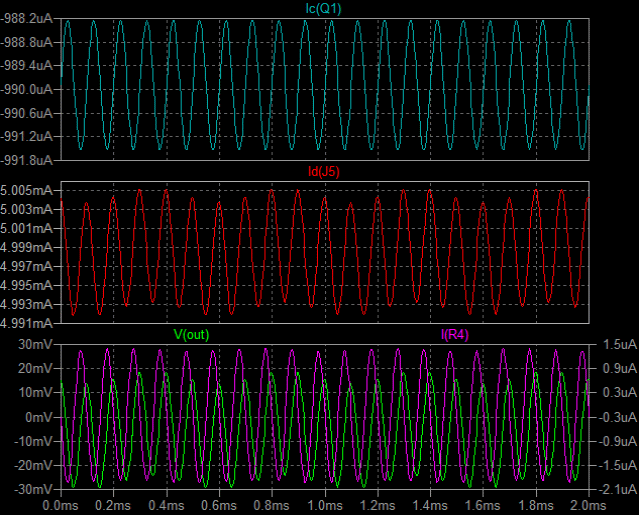 |
| ・さらに、J5の負電源も変動させます。 |
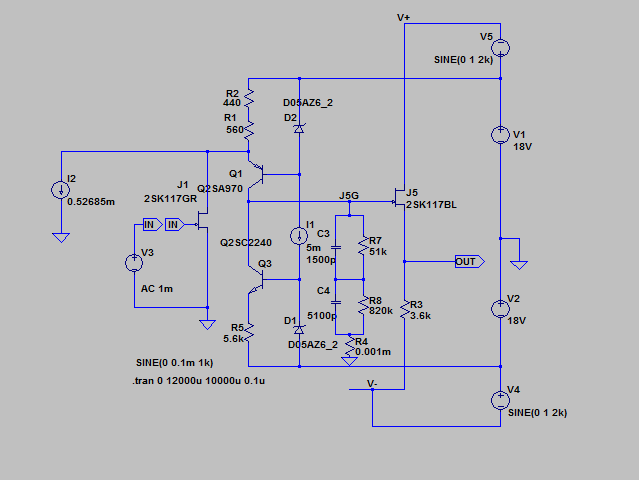 |
| ・Q1のコレクタ電流とEQ素子を流れる電流には影響がないですね。 ・が、J5のドレイン電流はもろに負電源変動の影響を受けて、2kHzの正弦波になってしまっています。 ・V(out)はかろうじて1kHzですが、歪んでますね。 |
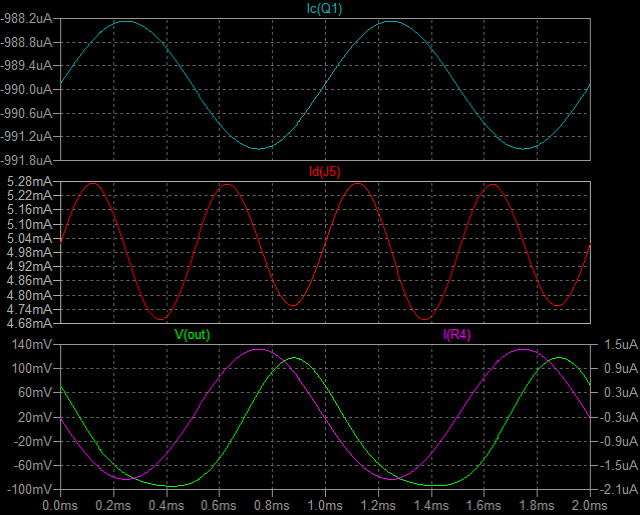 |
| ・入力を10kHzにするとさらに良く分かります。 ・V(out)も2kHzで変調されているんですね。 |
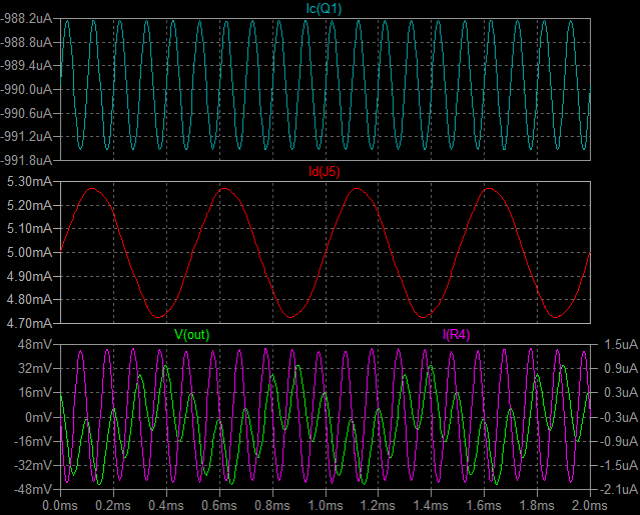 |
| ・EQ素子もJ5と同様に負電源側で変動させます。 |
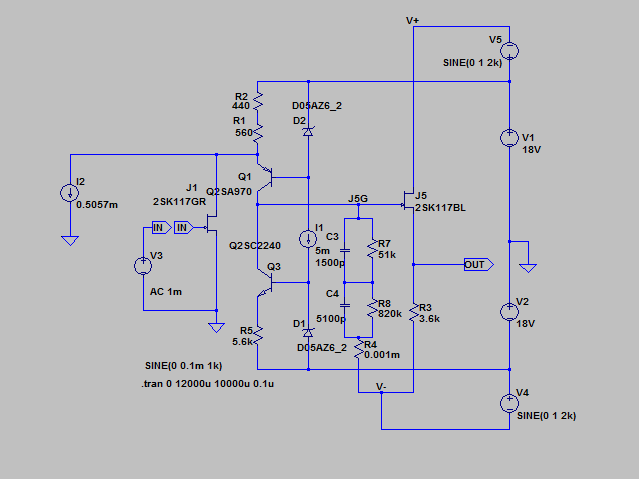 |
| ・これを見る限り、Q1のコレクタ電流、EQ素子を流れる電流自体が負電源変動の影響を受けて歪んでしまい、その結果J5のドレイン電流も歪んでしまうように思えます。 |
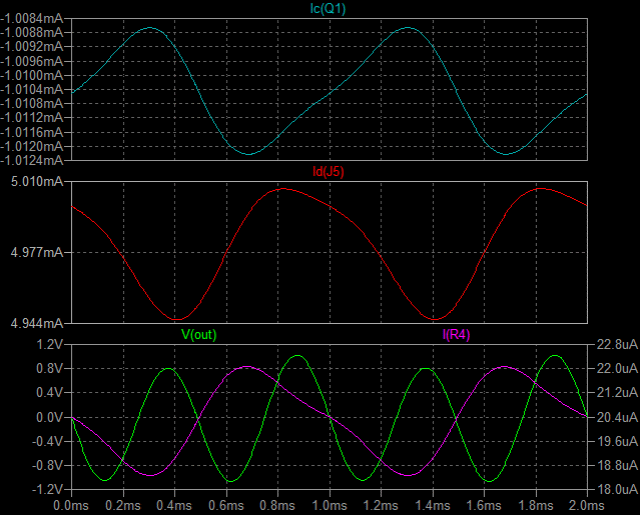 |
| ・入力を10kHzにしたものですが、やはり、Q1のコレクタ電流、よってEQ素子を流れる電流自体が負電源の2kHz変動で変調されているようです。 |
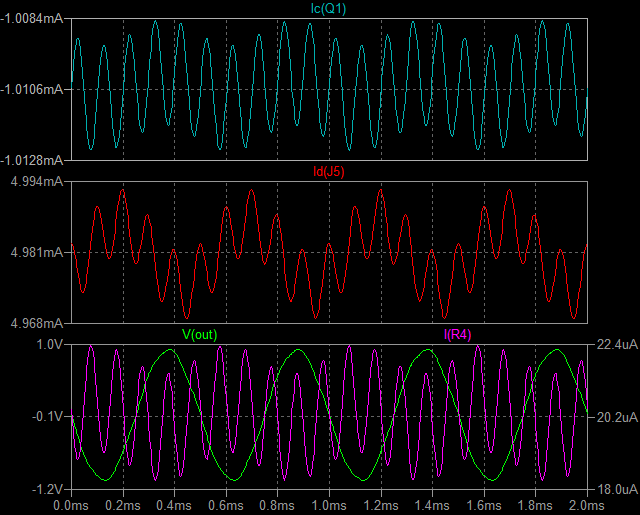 |
| ・念のため、正電源の変動をなくしてみます。 |
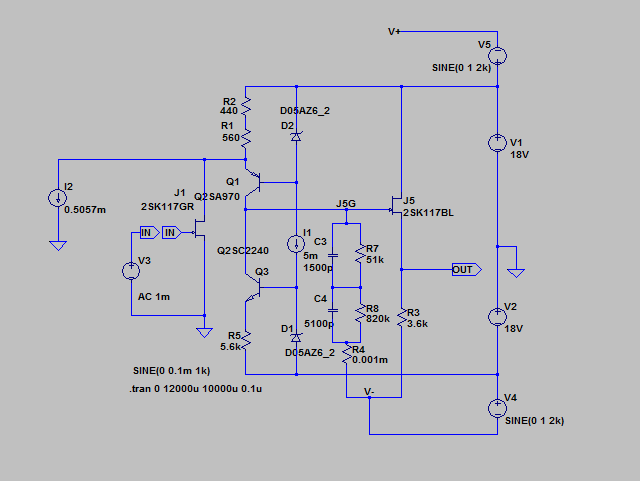 |
| ・同じですね。 |
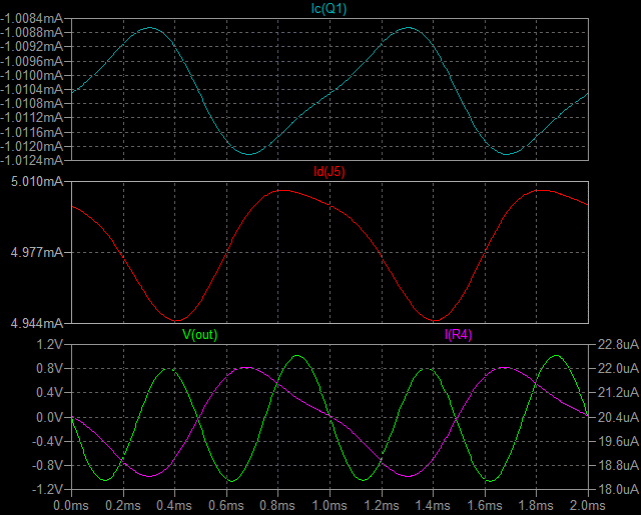 |
| ・10kHz。 ・同じですね。 |
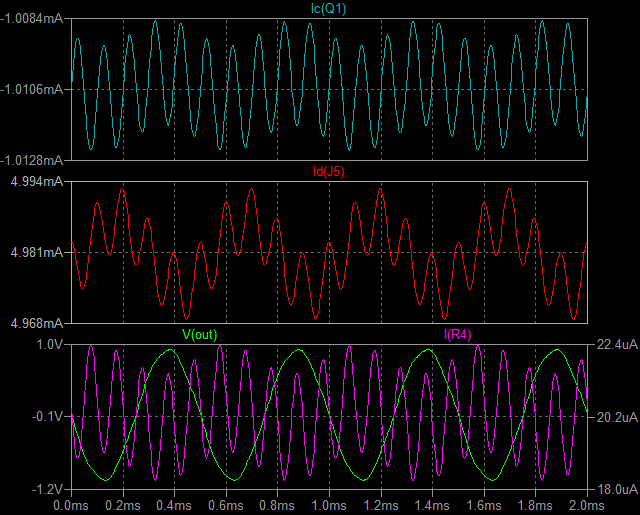 |
| ・この問題に対応しようとすれば、J5も対アース動作にするのが最良の手法。 |
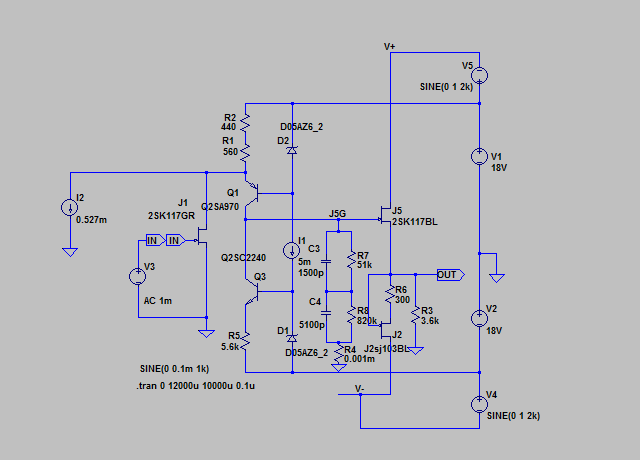 |
| ・目視では電源電圧変動の影響が確認できない。 ・が、 |
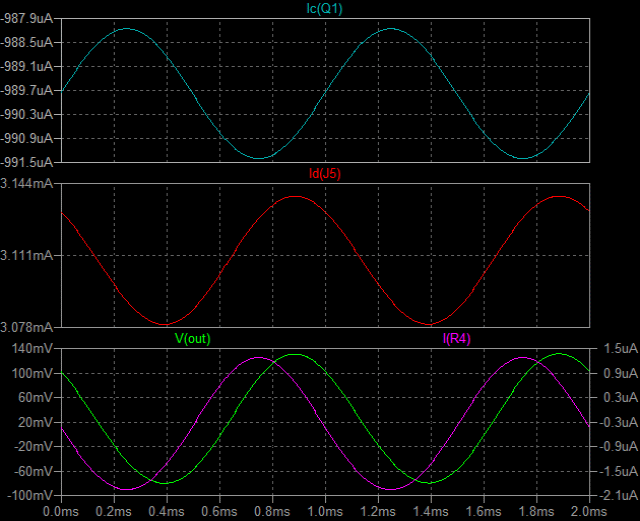 |
| ・入力を10kHzにしてみるとJ5のドレイン電流、J5ソース側の電圧出力とも2kHzの電源電圧変動により変調されていることが分かります。 ・ま、定電流回路といえども、そのインピーダンスを無限大にすることは不可能ですから止む無しです。 ・が、相対的には最良でしょう。 |
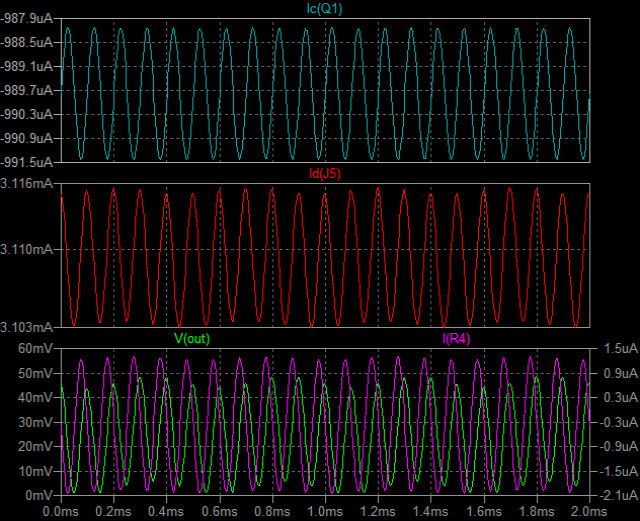 |
| ・ですが、初段プラス側にも電源電圧変動を加えると、 | 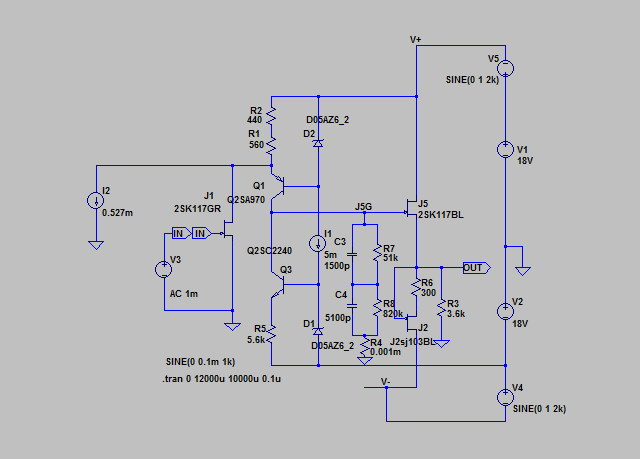 |
| ・どうにもなりませんね。 ・レギュレータの性能を信じる以外にない。(爆) |
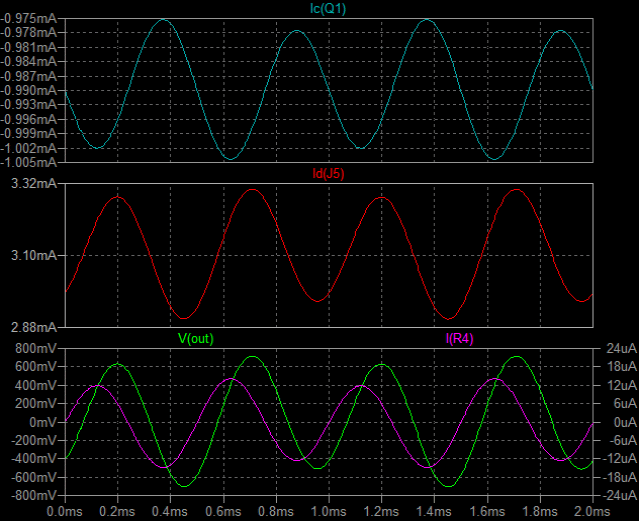 |
| ・J5を対アース動作にしても、Q1が対アース動作でなく対マイナス電源動作にすると、 | 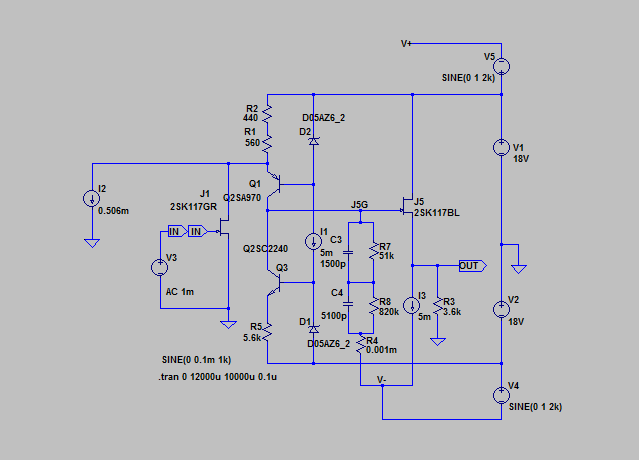 |
| ・Q1の電流、EQ素子に流れる電流とも負電源電圧の変動の影響を受けますし、J5のドレイン電流、ソース側の出力電圧とも対アース動作にした意味を失います。 |
 |
| ・何故でしょうね? ・これは入力10kHzです。 |
 |
| ・更にシンプル化A案です。 ・カレントラインアンプでの20dBの電流ゲイン分を、J5(2SK117BL)の電圧電流変換率を20dB上げて稼ぐことにより、カレントラインアンプ部を実質なくしたものですね。 ・モデルの2SK117BLのIdssは8.2mA程度ですので、定電流回路の設定は4mAです。Q3による定電流回路の設定は10mAです。 |
|
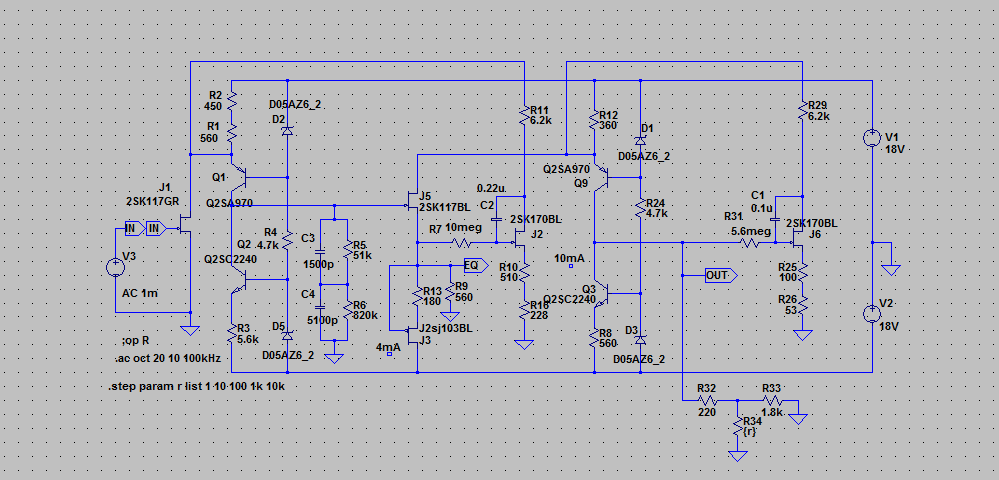 |
|
| ・緑がイコライザー部の電圧ゲイン。1kHzで59.6dBと、全体に1dB弱小さくなってますね。R9が560Ωと負荷が重くなったせいでしょうか。が、特に問題ではありません。 ・赤が、J5のドレイン電流で観たイコライザー部のgm(相互コンダクタンス)ですが、1kHzで4.66dBと、R9が5.6kΩの場合の10倍(+20dB)となっており、カレントラインで電流ゲインを加算する必要のないレベルになっています。 ・青がR33の電流で観たこのMCプリアンプの仕上がりのgm(相互コンダクタンス)ですが、ボリュームのR34が10kΩの場合3.1dB、1kΩの場合−4.4dB、100Ωの場合−21dB、10Ωの場合−40.6dB、1Ωの場合−60.6dBとなり、全体としてゲイン設定、ボリューム機能とも適切なものとなっています。 |
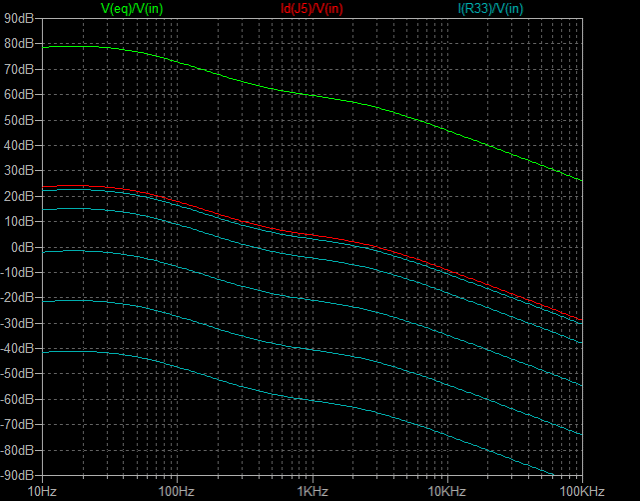 |
| ・が、kkomeさんおっしゃる通り課題がないわけではなく、J5の2SK117の動作電流がそのIdssで限られてしまう点が問題になります。 ・なかなかIdssの大きな2SK117がないですし、シミュレーションでもモデルのIdssが8.2mA程度なので、その動作点を4mAにしてありますが、そうすると当然J5のドレイン電流変化は4mA±4mAの範囲に限られますので、イコライザー部の出力電流も、このMCプリアンプの出力電流も±4mAの範囲に限定されます。 ・その影響を観ます。 |
|
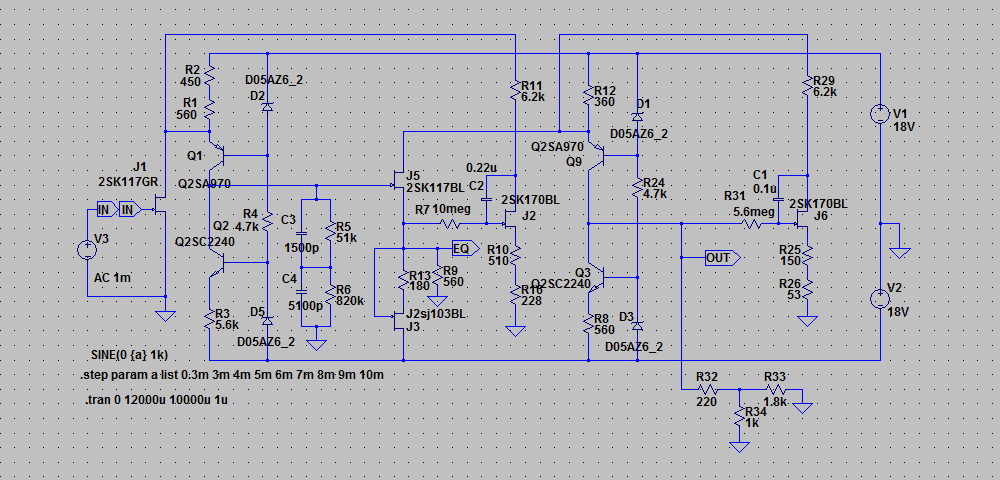 |
|
| ・カートリッジIVCに0.3mV、3mV,4mV、5mV、6mV、7mV、8mV、9mV、10mV、1kHzの正弦波を入力した場合の各部の応答を観ます。 ・上の表がQ9コレクタ部の出力電圧とR33の出力電流。 ・下の表がEQ部の出力電圧とJ5のコレクタ電流。 ・実は全て4mA×560Ω=2.24Vで決まってしまっていて、EQ部の出力電圧はマイナス側−2.24Vで飽和します。プラス側は電源電圧の範囲内で出力出来ているように見えますが、この場合2SJ117はプラスバイアスでの動作になるので、入力インピーダンスはトランジスタ並みに低下している可能性があり、妥当ではないでしょう。 ・結果、一番の問題は入力3mVに対応できていないという点ですね。許容最大入力は最低でも4mVは欲しいので、このままではちょっと無理です ・が、この簡素な回路は捨てがたいので、要はもっと電流の流せるFETを使用し、定電流回路での動作点電流を6mAにすれば4mV入力に対応できそうだし、倍の8mAに出来れば御の字のように思います。 |
 |
| ・例えば、こんな感じ。 ・思い切ってMOS−FET。とりあえずK教徒らしく2SK214ファミリーにしてみたものの、今はもっと適切なものがあるかもです。 ・動作点は10mAに設定。 |
|
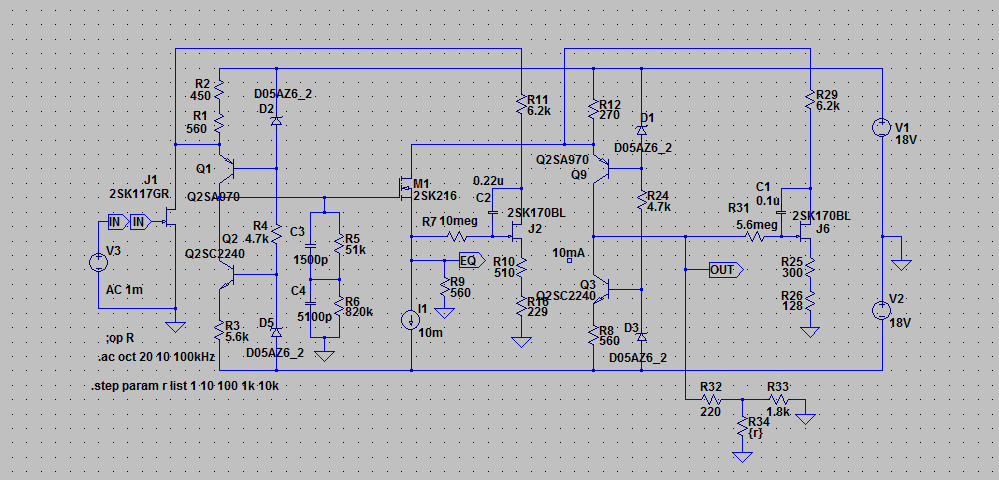 |
|
| ・緑がイコライザー部の電圧ゲイン。1kHzで60.22dB。 ・赤が、M1のドレイン電流で観たイコライザー部のgm(相互コンダクタンス)で、1kHzで5.3dB。 ・青がR33の電流で観たこのMCプリアンプの仕上がりのgm(相互コンダクタンス)ですが、ボリュームのR34が10kΩの場合3.7dB、1kΩの場合−3.8dB、100Ωの場合−20.5dB、10Ωの場合−40.0dB、1Ωの場合−60.0dB。 ・良いですね。 |
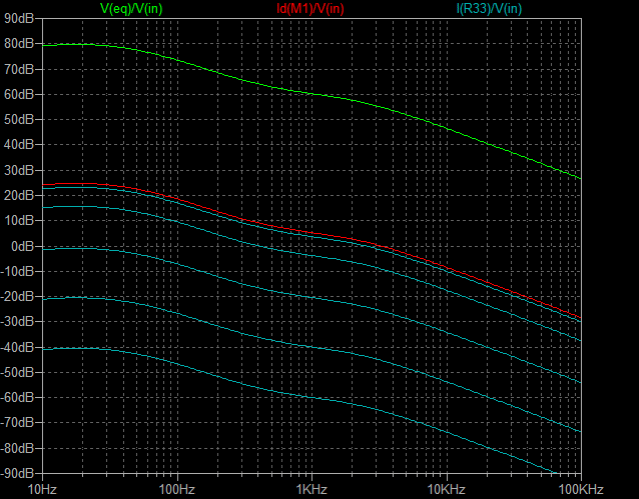 |
| ・問題の、カートリッジIVCに0.3mV、3mV,4mV、5mV、6mV、7mV、8mV、9mV、10mV、1kHzの正弦波を入力した場合の各部の応答を観ます。 ・上の表がQ9コレクタ部の出力電圧とR33の出力電流。 ・下の表がEQ部の出力電圧とJ5のコレクタ電流。 ・全て10mA×560Ω=5.64Vで決まってしまうのは同じですが、EQ部の出力も、最終出力電圧もR33の出力電流も、カートリッジIVC入力が5mVまでは対応出来ています。 ・これなら良いのではないでしょうか。 ・作って試してみたいですね。 |
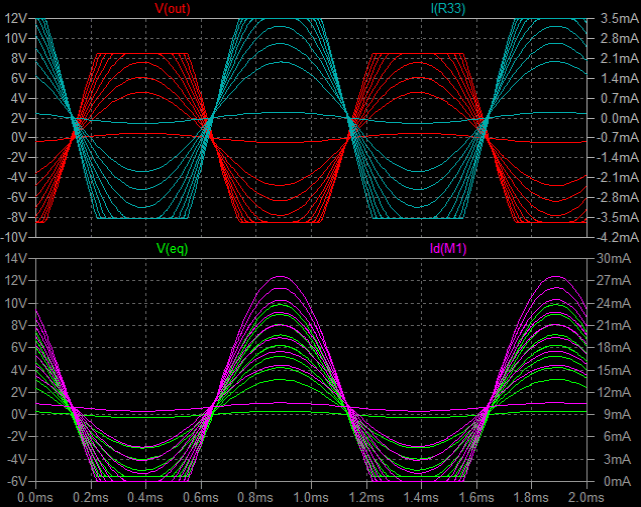 |
| ・Idssの大きなFETがない、さらにMOSも使いたくない、となれば、kkomeさんのB案になります。 |
|
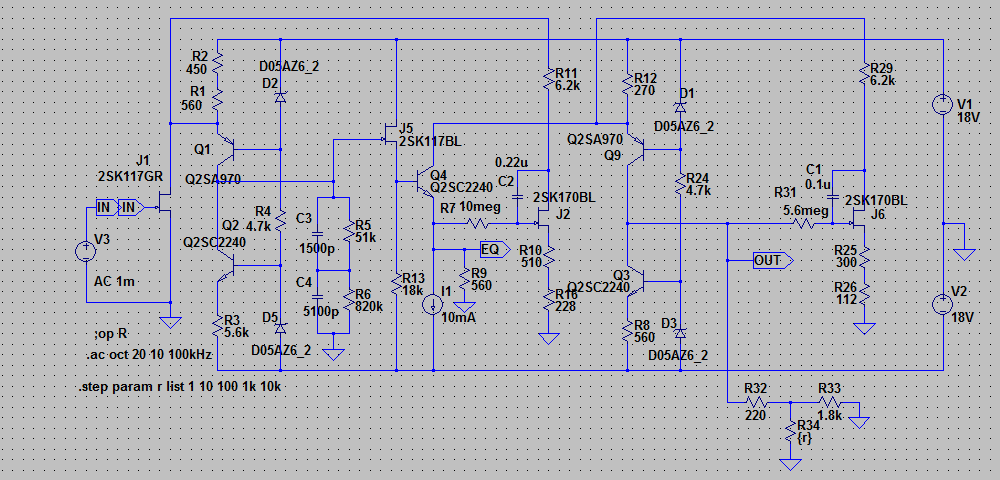 |
|
| ・Q4の動作点をMOSの場合と同じにしてあるので、結果も全く同じです。 |
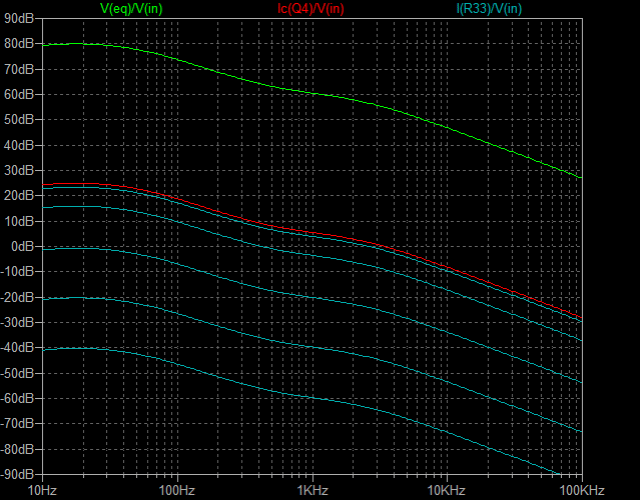 |
| ・カートリッジIVCに0.3mV、3mV,4mV、5mV、6mV、7mV、8mV、9mV、10mV、1kHzの正弦波を入力した場合の各部の応答も、上のMOSの場合と全く同じです。 ・ただ、これだとアンプ部のトランジスタ数は同じなので、簡素化という意味ではいまいちでしょうか。 |
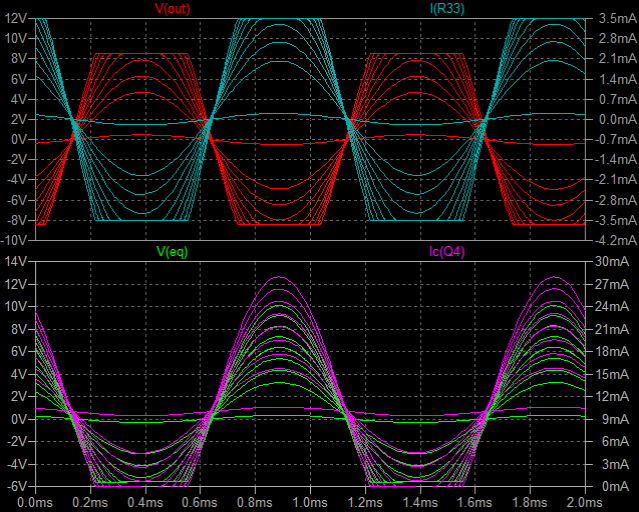 |
| ・では、勝負。 |
|
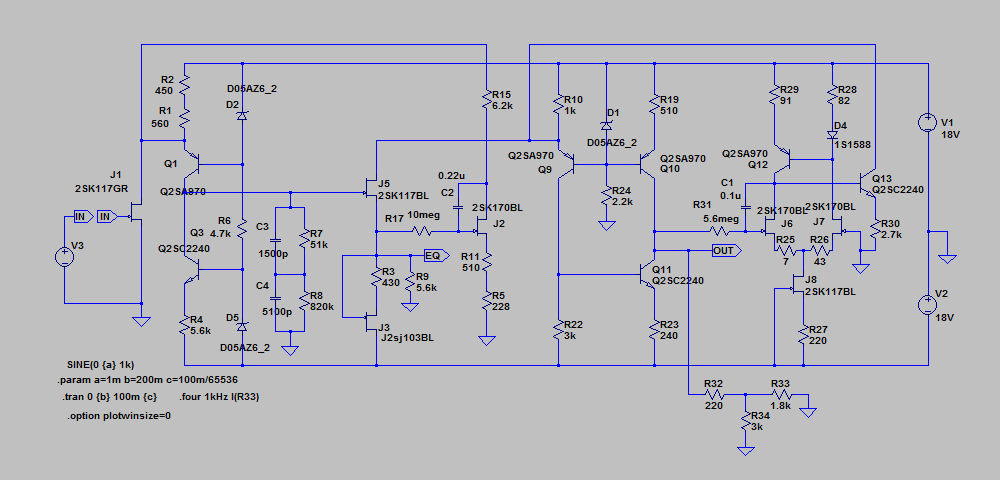 |
|
| ・まずは既に製作済みの簡素版No−248もどきIVC型MCプリアンプ。 ・カートリッジVICの入力に1mV1kHzの正弦波を入力し、ボリュームR34を調整してR33に1mA1kHz正弦波を出力させた場合のその歪率をFFTで観ます。 ・結果が右で、二次高調波が−58dB程度、三次高調波が-80dB程度。 ・Total Harmonic Distortion=0.132154% ・無帰還なのでこんなところ。 |
 |
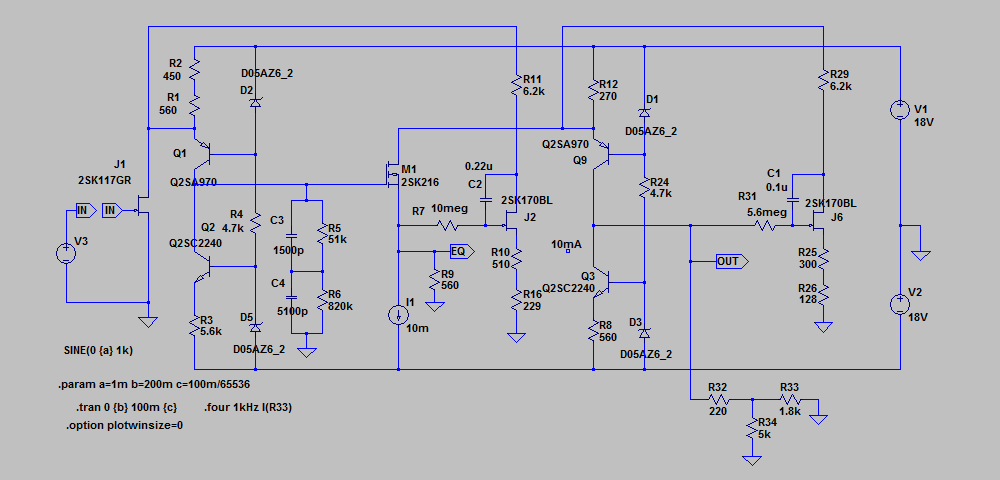 |
|
| ・次はkkomeさんA案。 ・結果が右ですが随分良さ気。 ・二次高調波が−72dB程度、三次高調波が-83dB程度。 ・Total Harmonic Distortion=0.028448% ・あらららら。素晴らしい。歪率1桁少ないですね。 |
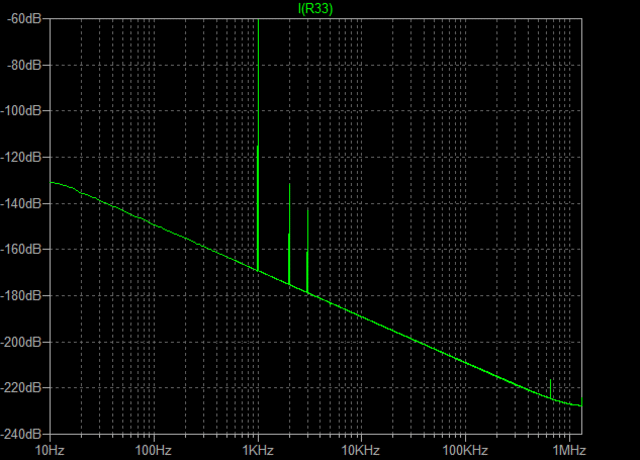 |
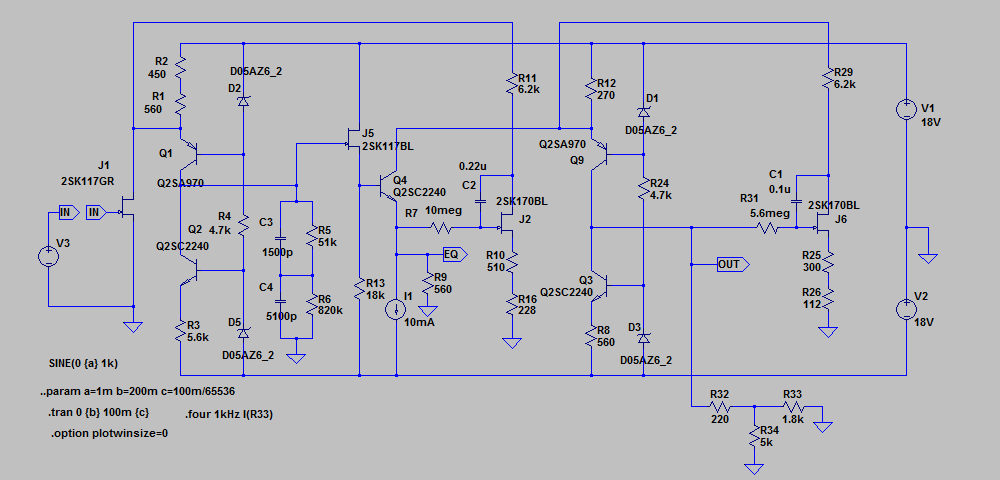 |
|
| ・次はkkomeさんB案。 ・結果が右。 ・これも良さ気。 ・二次高調波が−69dB程度、三次高調波が-86dB程度。 ・Total Harmonic Distortion=0.035902% ・こちらも素晴らしい。 ・う〜ん、一番簡素で歪率最良のA案、作りたくなってきました。 |
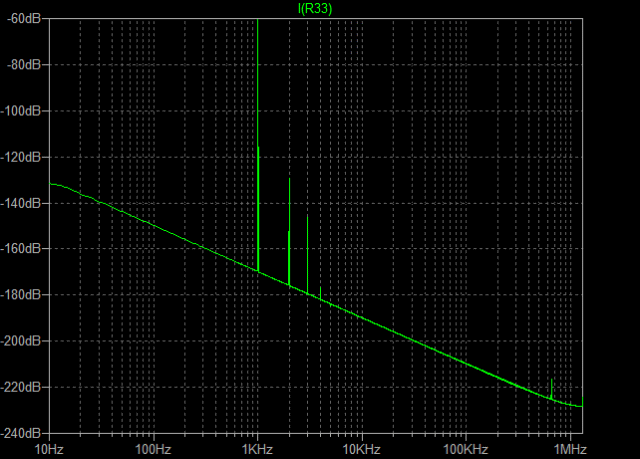 |
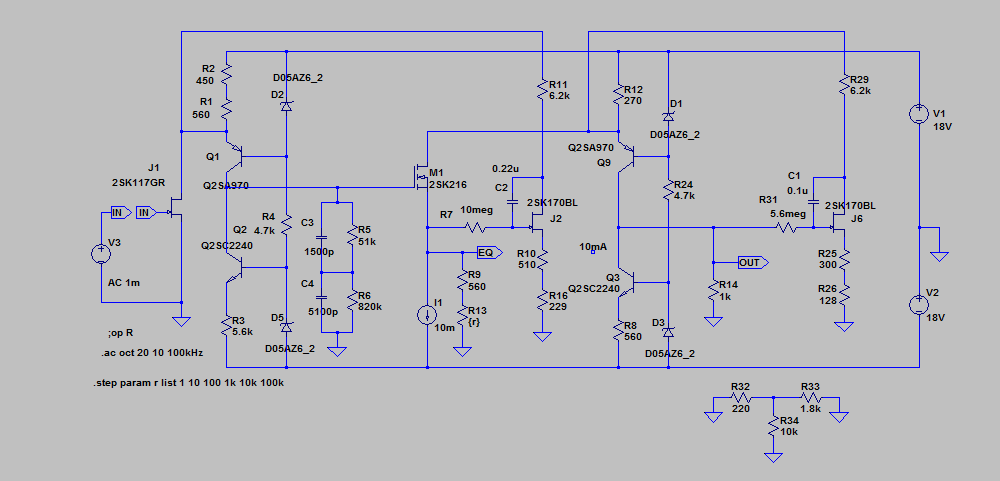 |
|
| ・次は、A案のM1による電圧電流返還率を変えることでボリューム調整をする案です。 ・結果は右の通りで、赤と青が重ねってますが、赤がM5のドレイン電流で観たイコライザー部のgm(相互コンダクタンス)で青が出力部の抵抗R14の電流で観たこのMCプリのgm(相互コンダクタンス)です。これらが重なるのは当然ですね。 ・この場合は上からボリュームであるR13が1Ω、10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩ、100kΩの場合です。 ・適切な状態ですので、これも可ですね。出力のR14はないとSAOCが働かなくなるので、適宜調整すれば良いのではないでしょうか。 ・ボリュームが100kΩでも-40dBまでしか下がらない点は課題ですかねぇ。 |
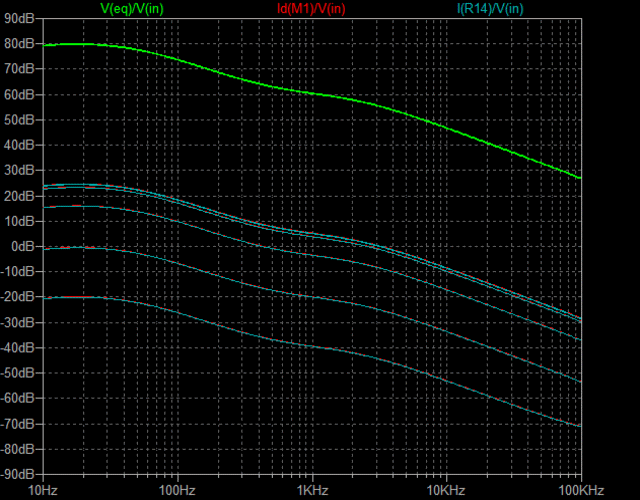 |
| ・もっと簡素化してみました。 |
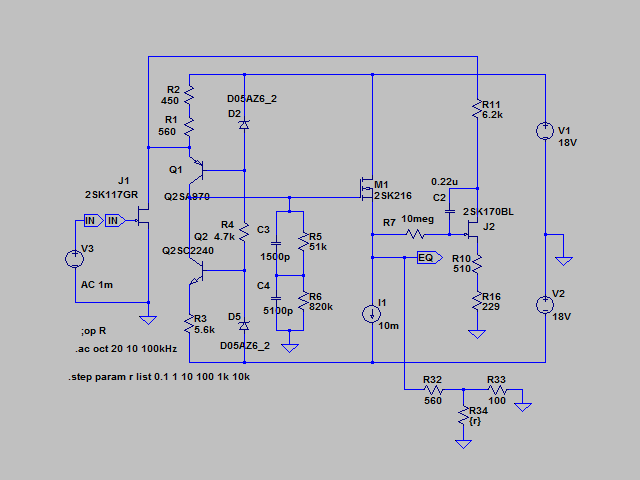 |
| ・結果はこうです。 ・ゲインは当然十分ですし、R33の電流で観たこのMCプリのgm(相互コンダクタンス)も適切な調整範囲です。青の上、10kΩと1kΩの場合が近いことで分かりますが、これだとボリュームR34は1kΩで良いですね。 |
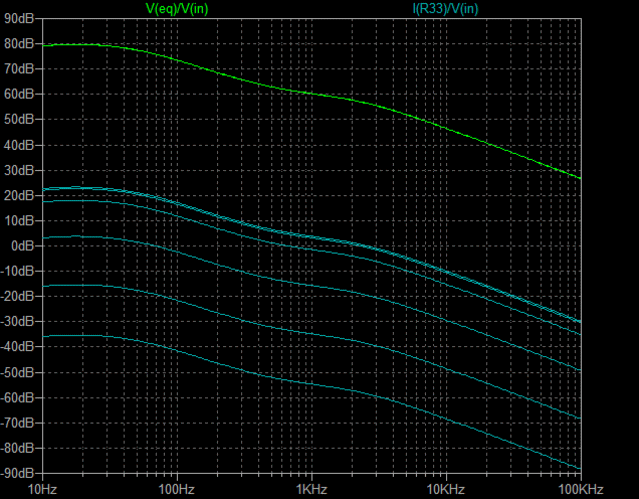 |
| カートリッジIVCに0.3mV、3mV,4mV、5mV、6mV、7mV、8mV、9mV、10mV、1kHzの正弦波を入力した場合の応答。 |
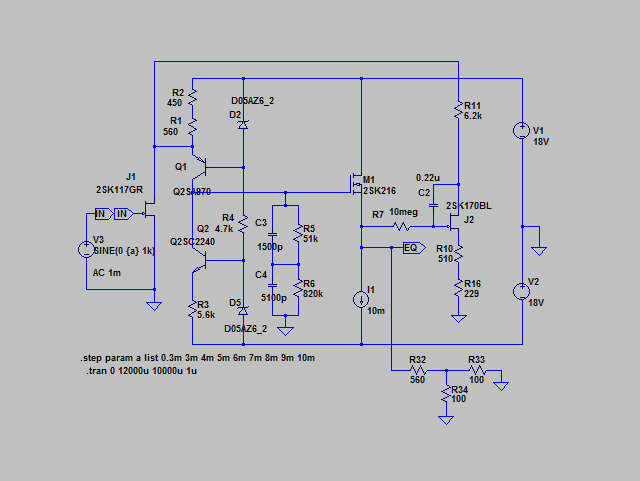 |
| ・ボリュームR43が100Ωの場合ですが、出力電圧もR33の出力電流も、入力6mVまで対応できていますね。 ・良いのではないでしょうか。 |
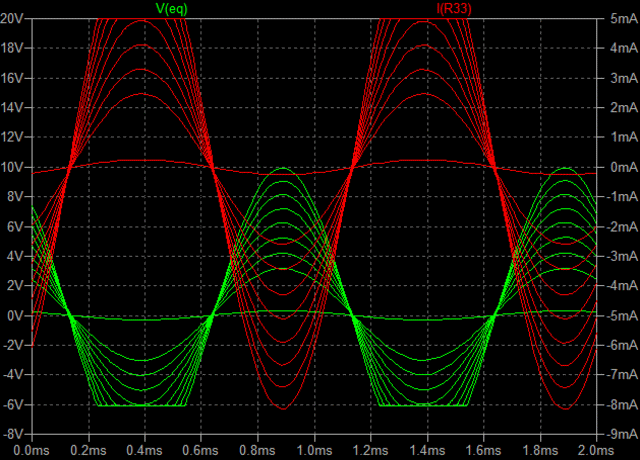 |
| ・歪率はどうでしょう。 |
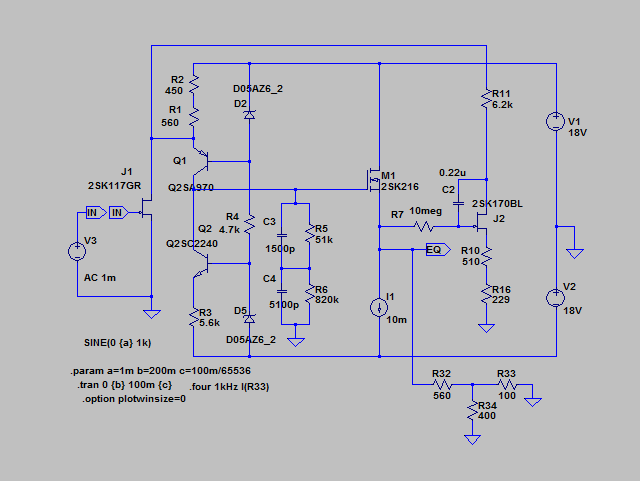 |
| 結果が右。 ・二次高調波が−68dB程度、三次高調波が-92dB程度。 ・Total Harmonic Distortion=0.043585% ・こちらもよいですね。 ・う〜ん、これも作りたくなってきました。 |
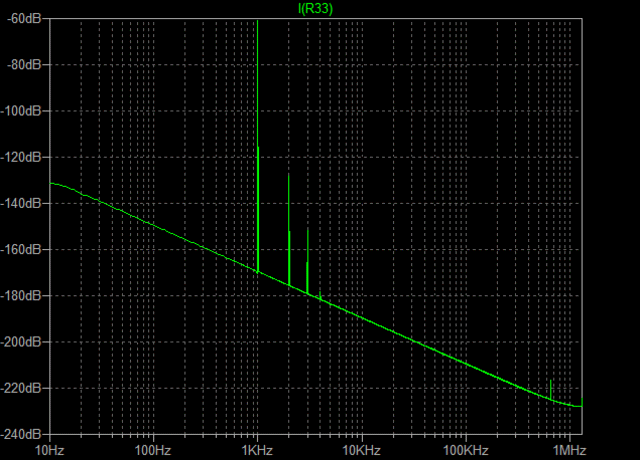 |